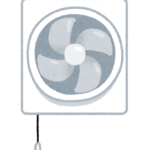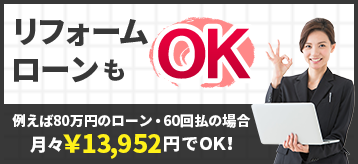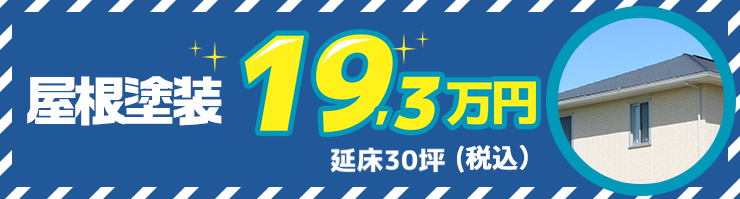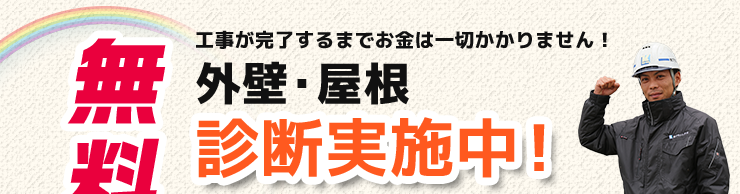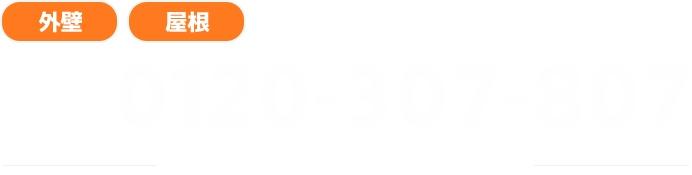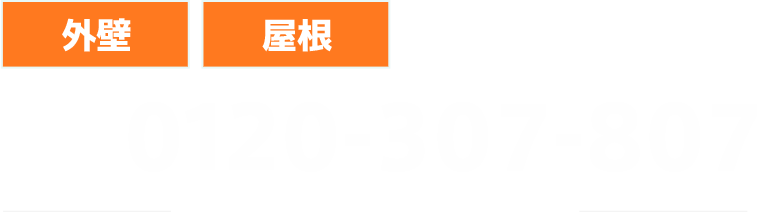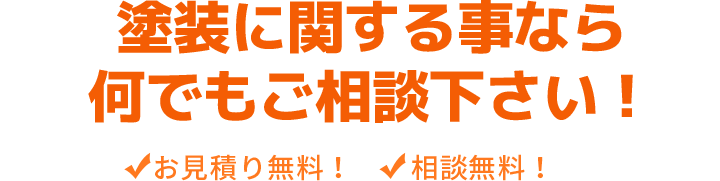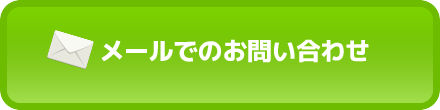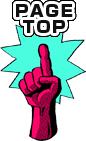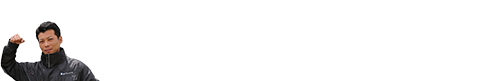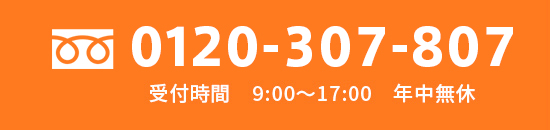- HOME
- >
- ブログ
ブログ
2020年6月4日
防水リフォームは必要か?
住宅の新築時には防水が施されていますが、経年劣化により防水層の性能は低下していきます。防水性能が失われると建物内部に雨水が侵入することとなり柱や梁といった木部が腐ってしまう事態を起こしてしまいます。このことから防水リフォームは必要ということです。
今回は防水リフォームがなぜ必要なのか、どのような防水リフォームがあるのかを見ていきましょう。
防水リフォームはなぜ必要?
経年劣化により防水層の性能が低下している状態でそのままにしておくと、建物内部に侵入した雨水により雨漏りが起きたり、壁内部の柱を腐らせてしまう事態をまねきます。
明らかに雨漏りがしている状態ですと防水層が劣化していることに気づくことはできますが、症状がない場合は防水層の劣化にはなかなか気づかないものです。
10年以上何もメンテナンスをしていない場合は防水層の劣化を疑ってもみましょう。
まずは防水リフォームの知識と経験のある専門業者へ現状調査を依頼しましょう。
防水リフォームの種類
防水リフォームには使用する材料や工法により、いくつかの種類があります。
■シート防水
シート防水とは、塩化ビニール樹脂などで作られたシートを貼りつける工事をいいます。
下地に接着剤を塗って貼りつけていく施工で、工期は短くてすみ、防水シート自体も頑丈なため防水層が剥がれにくいメリットがあります。
ロール状のものが大半で、複雑な形状に施工するのが難しいのがデメリットです。
ビルの屋上など広い面積を施工する際によく採用されています。
■FRP防水
FRP防水とは、ガラス繊維製のシート樹脂を塗って施工する工事です。
ガラス繊維で強化されたプラスチックとなるため耐久性が高く軽量なことがメリットです。
紫外線で劣化するため、メンテナンスをしないままだと防水性が低下してしうデメリットをもちます。
定期的にトップコートを塗布すれば防水性を保つことができます。
■ウレタン防水
ウレタン防水とは、ウレタン防水剤を塗布する防水工事です。
塗装と同じように液体を塗って施工するため、複雑な形状のところや狭いところも施工できるのがメリットです。
塗装と同じで耐久性がやや低く、耐用年数も短いのがデメリットとなります。
■アスファルト防水
アスファルト防水とは、コールタールを染み込ませたシートを貼りつける防水工事です。
道路と同じアスファルト材料を使用するため耐久性が高いのがメリットです。
重量が重くコールタールを加熱するときの臭いがデメリットとなります。
まとめ
住宅の状態を長く安全に保つためには、定期的な防水層のメンテナンスが必要です。この記事を読んで10年以上メンテナンスを何もしていないという方は、一度専門業者に現在の状態の確認のために調査依頼をしましょう。大切なのは専門業者に依頼するということです。防水工事には種類があり施工方法もそれぞれ違います。経験と知識が豊富な専門業者だと施工不良が起きる可能性も少なく安心して任せることができるでしょう。
2020年6月3日
雨から屋根を守る最強建材 防水シート
梅雨の長引く雨や、台風を伴う強い大雨から屋根を守ってくれているのが防水シートです。屋根材などに問題がある場合は雨漏りを防ぐべき最強の働きをしてくれる、たいへん優秀で重要な建材です。
今回は屋根の防水シートについて詳しく見ていきましょう。
屋根の構造
屋根は下から、野地板・防水シート・屋根材の順に重なっています。
野地板には木を主とした合板やコンパネが使われています。
築年数が古い瓦屋根の場合は防水シートは使用されずに、土が敷きつめられていることがあります。
これを土葺き工法といい、少し前の瓦屋根ではよく使われた工法です。
防水シートとは重要
屋根材の下に敷く防水シートはルーフィングシートとも呼ばれます。
防水シートは、梅雨の長引く雨や、台風を伴う強い大雨による雨水の侵入を防いでいます。
隙間から入り込んでしまった雨は防水シートがあることで排水され、深部に侵入することはできません。
一方、防水シートがなければ雨水は野地板や天井に浸み込み、柱や梁といった木材にまで被害が及ぶことになります。
防水シートは大切な家を守るためには必要不可欠な建材なのです。
しかし防水シートも劣化します。
劣化した状態で放置すると雨漏りリスクが高まり危険です。
防水シートの劣化のサインは早い段階で見つけて対処しましょう。
防水シートの劣化サイン
防水シートの劣化は目視で確認できます。
下記のようなサインが確認できたら、専門業者へ調査依頼をしましょう。
<防水シート劣化サイン>
■防水シートが膨れたり、浮いてたりする
防水機能を失っている可能性大⇒防水シート交換工事
■防水シートにひび割れがある
部分的なひび割れ⇒劣化部分のみ修繕
■草が生えている
防水機能を失っている可能性大⇒防水シート交換工事
■雨水が溜まっている
防水機能を失っている可能性大⇒防水シート交換工事
防水シートの修繕と交換
防水シートにひび割れや膨れ、浮きなどの劣化サインが確認できた際は、まずは部分的な劣化サインなのか全体的な劣化サインなのか見極めましょう。10年以上メンテナンスをしていない場合は全体的な劣化のサインと考えられます。その場合は既存の防水シートを完全に撤去してから新しい防水シートの張り付けをしましょう。
部分的なひび割れの劣化サインは劣化部分のみ張り替えをします。ただ、部分的な補修をしてもつなぎ目や他の古い防水シートは経年劣化をしていくので、何度も修繕を繰り返すことになりかねません。
「何度も工事は嫌だわ…」と考える方は、今後のことを考えて全部張り替え交換を選択した方が良いでしょう。
まとめ
大雨や強い横殴りの雨から屋根を守っている防水シートは、雨漏りリスクを高めないためにもきちんとメンテナンスをしましょう。雨漏りが起こってしまってからでは、メンテナンスでかかる費用以上に費用はかさみます。
雨が続く梅雨や台風の時期に備えて、防水シートのメンテナンスを考えてみませんか?
カテゴリ:屋根
2020年6月2日
人気の屋根材の種類とメリット・デメリット
一般の住宅に使用される主な屋根材には、日本瓦、セメント瓦、スレート材、ガルバリウム鋼板の4種類があります。
今回は各屋根材の特徴と、メリット・デメリットを見ていきましょう。
屋根材の種類
■日本瓦
日本瓦とは、粘土や土を高温で焼き形成して作る、和風の瓦です。
表面を釉薬で覆った「釉薬瓦 ユウヤクカワラ」や釉薬が塗られていない「いぶし瓦」があります。
■セメント瓦
セメントと砂を主原料とした加圧して成形、乾燥させた瓦です。
日本瓦よりも安価で寒暖の影響をうけにくいといわれいます。
■スレート材
繊維とセメントを板状に成型してつくる屋根材です。
天然の粘土を使ったものは「天然スレート」と呼ばれ高価な屋根材となります。
「カラーベスト」や「コロニアル」と呼ばれる商品が有名です。
■ガルバリウム鋼板
アルミと亜鉛の合金でメッキ処理を施した金属系の屋根材です。
各屋根材のメリットとデメリット
■日本瓦
メリット:重厚感があり日本家屋を象徴する屋根材
メリット:50年以上の耐久性
デメリット:他の屋根材と比べると非常に重い
デメリット:瓦の割れや、接合部分の漆喰の点検が必要。放置すると雨漏りの原因になる
■セメント瓦
メリット:和風・洋風どちらのデザインにも対応できる
メリット:施工費用を抑えることができる
デメリット:他の屋根材と比べると非常に重い
デメリット:日本瓦と違い、表面の塗装が必要。塗装が劣化すると瓦自体の劣化につながる
■スレート材
メリット:シンプルなだけに、どんなデザインにも馴染む
メリット:断熱・遮熱性能を有している
メリット:軽量で屋根にかかる負荷を軽減
デメリット:耐久性を保つために10年程度に一度の塗装が必要
デメリット:スレート材そのものの点検も必要(5年に一度程度)
■ガルバリウム鋼板
メリット:最も軽い屋根材
メリット:軽量なため施工しやすい
メリット:建物に負荷をかけない
デメリット:表面に傷ができるとサビが出る
デメリット:熱を伝えやすく、雨音も響きやすい
まとめ
それぞれの屋根材にメリットとデメリットがあります。まずは既存の屋根材の状態を知り、屋根のリフォームを検討の際は「葺き替え」にするのか「カバー工法」にするのか、また既存の屋根にはどのタイプの屋根材がリフォームに適しているのかを、プロの業者に診断をしてもらいましょう。
カテゴリ:屋根
2020年6月1日
ガルバリウムの家は塗替えの必要がないって本当?
ガルバリウム鋼板の外壁は塗替えの必要がないと聞いたことはありませんか?
外壁塗装リフォームにかかる費用は高額なため、塗替えが不要になると費用的な負担も軽減できます。
では、本当にリフォームが不要なのかご説明します。
ガルバリウム鋼板とは何?
ガルバリウム鋼板は金属系のサイディングの一種で、鉄でできた板に金属メッキで加工した金属質の板のことです。主に外壁材や屋根材に使用されています。
シンプルモダンな印象と独特のデザイン性で、近年ガルバリウム鋼板を使用した住宅や建物が増えてきています。
◆特徴
ガルバリウムで最も使用されているのは 『 黒色 』です。圧倒的な存在感と重厚感が人気の理由です。色の種類は豊富ですがメーカーによって様々です。
艶ありと艶消しがあり、艶ありは自然光の反射によって光沢を放ちます。
艶消しはマットな質感で落ち着いた印象を与えます。
◆メリットとデメリット
〇メリット
・錆びにくい
・耐久性が高い
・耐震性が高い
・デザイン性が高い
・耐熱性が高い
×デメリット
・メンテナンスコストがやや高い
・断熱性が低い
・遮音性が低い
塗替えの必要性について
◇塗替えの頻度
同じガルバリウム鋼板を使用しても、住む環境や地域の気候によっても違いが生じます。
屋根や外壁塗装は単に色を塗り替えるという目的以外に、外的環境から住宅を守るための塗膜を作るということも含まれています。
経年劣化により塗膜は剥がれてしまいます。剥がれが生じると、ガルバリウム鋼板自体に錆びや色あせが起こります。したがって10~15年周期で定期的なメンテナンスは必要ということになります。
◇相場
外壁塗装の相場は約80万~120万円です。
屋根や外壁塗装では高所での作業を伴うため、足場の仮設が必須になります。
ガルバリウム鋼板は表面に凹凸があるものが多く、熟練した職人の技術が必要です。材質の特性上合わない塗料もあるので使用する塗料選びも重要です。
まとめ
ガルバリウム鋼板の特徴はご理解いただけたかと思います。
住宅は強い紫外線や雨風などの外的環境にさらされており、ガルバリウムの高い耐久性と耐用年数が長いという優れた特徴は大きな強みと言えます。
ですが、耐用年数が長い=メンテナンスが不要ということではありません。
定期的なメンテナンスで大切な家を守りましょう!
カテゴリ:外壁
2020年5月31日
デザイン重視!お洒落な屋根にしたい!
家の外観にこだわる方の中には外壁に続き屋根にポイントを置く方も多いです。一括りに「屋根」といっても、どのような屋根がお洒落に洗練された屋根にみえるのでしょうか。
ここでは、お洒落に見える屋根を紹介していきます。
お洒落に見える屋根
■『切妻屋根』シンプルが和洋どちらでも合う
切妻屋根は、屋根の中心部分を頂点として二枚の屋根が繋がっている形状の屋根です。
子供がお絵かきなどで書く、三角屋根の形といえばイメージがわくでしょう。
切妻屋根は、屋根の傾斜を変えることで印象がかわります。緩い傾斜にすると、どっしりとした印象、反対に急傾斜にするとシャープな印象となります。
屋根材とも相性がよく、日本瓦から洋風瓦、スレートまでさまざまな屋根材を自由に使用することができることからデザインの自由度は高くなります。
軒先が張り出す形状ですので、張り出しの大きさや、軒下や破風などのデザインで和風な印象になったり、洋風な印象になったりと自分好みの屋根を作ることができるでしょう。
■『陸屋根』勾配のない屋根
陸屋根は、屋根の勾配をなくした屋根です。
綺麗な四角形の建物が人気となってきているなか、よく採用されています。屋根部分を屋上として利用するなどモダンな印象です。
陸屋根は屋根に傾斜はありません。そのため排水口からスムーズに雨水を排水できなくなると、雨漏りのリスクは高くなります。
■『片流れ屋根』モダンでシャープな印象
片流れ屋根とは、一枚の屋根を斜めに配置した屋根の形状のことです。
斜めにスパッと切り落としたようなイメージで、建物をシャープな印象にします。
また屋根の面積を小さくすることができ、土地が狭い場合には適している屋根といえます。
最近の新築物件では、よく見られる人気の屋根です。
モダンでお洒落な家にするために
屋根の形状で建物の印象はがらりと変わります。
屋根の勾配を緩くすると柔らかさや重厚感が生まれ、急勾配ならシャープさを感じ取れます。
軒は外壁のデザインや屋根のカラーによっても印象は大きくかわりますが、張り出していた方が重厚感があり、短くするとシャープな印象となります。
屋根の勾配や色については、少しの違いで建物全体の印象は大きく変わることからリフォームの際は、じっくりと組み合わせを検討しましょう。
まずは、業者へ依頼する前に住宅展示場や工務店のホームページなどを参考にして、自分のイメージするものを見ることが業者との打合せの際には生きてきます。参考資料などは事前に用意しておきましょう。
まとめ
屋根の形状でがらりと印象が変わってしまう建物ですが、屋根の形状が決められないという方は建物全体のイメージを考えてみましょう。「シャープで洗練された印象の家にしたい」「外国の家のようにかわいい印象にしたい」「シックでモダンな建物にしたい」など、自分の描くイメージを追求してみましょう。
プラニング・Kでは、豊富な知識であなたのリフォームのお手伝いをさせていただきます。お気軽にお問合せ下さい。
カテゴリ:屋根
2020年5月30日
外壁コーディネート ~ vol.2 テクスチャー編 ~
外壁の種類により住宅のイメージは左右します。外壁には色の塗替え以外に、使用する外壁材の材質や質感で外壁のイメージを表現することもできます。素材選びは外観デザインの大きなポイントになります。
では早速、どのようなコーディネートがあるのかご紹介します。
外壁材の種類と特徴
外壁は経年劣化の影響を受けやすいため、防水性や耐久性が必要になります。
まずは一般的に使用されている外壁材の種類と特徴を知りましょう!
| ●窯業用サイディング
セメントと繊維質などの原料を形成したもの。 |
〇メリット
・デザイン性が高く、美しい柄や色が豊富。 ・耐久性が高く、コストパフォーマンスが良いことから人気の材質。
×デメリット ・つなぎ目にシーリング材を使用しているため、経年劣化によりシーリング材のひび割れが生じる。 |
| ●金属系サイディング
裏面には断熱材を使用し、金属板を成形したもの。 |
〇メリット
・耐水性が高い。 ・寒い地域での凍害の影響も受けにくい。 ・断熱性や防音性に優れている。 ・外壁材の中でも軽量で、重ね張りするリフォームでの使用も増えている。
×デメリット ・費用は高めだが、メンテナンスの頻度は少ない。 |
| ●モルタル
セメントと砂を混ぜ合わせた素材 |
〇メリット
・防火性に優れている。 ・混ぜ合わせた素材を職人が塗り上げていくので、手仕事の風合いを感じる。 ・仕上げ方によって様々な表情になる。
×デメリット ・材質が硬く、地震などによる衝撃でひび割れが生じやすい。 |
| ●タイル
粘土などの原料を焼き固めてつくられたもの。 |
〇メリット
・耐久性や耐候性に優れている。 ・硬く傷がつきにくい。 ・防水性が高く、雨水も吸収しないため耐用年数も長い。 ・重厚な印象が高級感を演出する。
×デメリット ・高級な材質のため、費用も高額になる。 |
| ●ALC
軽量の気泡コンクリート素材 |
〇メリット
・耐久性が高い。 ・断熱性に優れ、夏は涼しく冬は暖かい。 ・耐火性に優れている。 ・遮音性が高く、防音壁として使用されることがある。
×デメリット ・費用が高い。 ・防水性が低いため、防水性の高い塗料で塗装を行い保護する必要がある。 |
テクスチャー(材質)の選び方
テクスチャーとは、材料の表面の視覚的な色や明るさの均質さ、触覚的な強弱を感じる凹凸といった部分的変化を全体的にとらえた特徴や材質感覚、効果を指します。
では実際にどのような組み合わせがあるのかご紹介します。
◆左右張り分け
2種類の材質を使用し、縦に張り分ける方法。
上下に目線がいくので、シャープにすっきりとした印象を与えます。
◆上下張り分け
1階と2階で柄の違う質感で張り分けることで安定感を与えます。
上下どちらかに凹凸感のある素材を選ぶとメリハリが出て、より立体感を演出できます。
◆全面張り
1種類の外壁材で全面張りにすることで統一感のある落ち着いた印象になります。
例えば下の画像のように同じ柄でトーンに変化をつけ張り分けすると、上品な中にもアクセントが生まれます。
まとめ
材質でイメージを変えるというのはどうしても難しく感じてしまいますが、外壁材の特徴を活かした組み合わせで素敵に大変身します。
外壁材は材料費と耐久性のバランスが大切です。外壁リフォームを検討する際には、いかに外壁材の種類や特徴を理解した上で選択するかが外装コーディネートの成功に繋がります。
理想の材質の組み合わせや張り分けを見つけ、魅力的な外観を作りましょう!
カテゴリ:外壁
2020年5月29日
下塗り用塗料「プライマー」とは?
外壁や屋根の塗装工程の中で、下塗りプライマー塗装という工程があります。塗装する上で大変重要な作業工程の一つです。このプライマー塗装の出来が最終的な塗装の仕上りを左右するともいわれています。
ここでは下塗り用塗料プライマーについて紹介します。
プライマーとは
プライマーとは、簡単にいうと下塗り用塗料のことです。
塗装は、下塗り・中塗り・上塗りと3回塗りが基本となっていて、塗膜の厚みをつくり塗料を剥がれにくくしています。
プライマー塗装は、外壁や屋根の塗装をする際に最初に行う下塗りのことで、中塗りや上塗り塗料の密着性を高める接着剤のような役割を持ち、塗装面を整える重要な役割も兼ねています。
プライマーの種類
下地の状況やもともと塗られている塗料によって、適しているプライマーを使い分けることが必要です。
上塗り塗料と同じくプライマーにも水性タイプと油性タイプがあり、水性タイプは塗装時の臭いが少なく環境に対する影響も少ないのが特徴です。一方、油性タイプは浸透性が高く下地補強、密着度が水性タイプよりも優れていますが、塗装時の臭いは強いです。
浸透性プライマー
浸透性プライマーは劣化している塗装面の奥深くまで浸透して下地を補強することが特徴の下塗り用塗料です。
建物の内装にも使用するこが可能で、コンクリートやセメントモルタル、スレートなどに塗布して表面を強化させるために使用することもあります。
防錆プライマー
防錆プライマーは鉄部の下塗り用塗料です。鉄部の塗装はサンドペーパーやワイヤーブラシで錆を落としてから防錆プライマーを塗ります。そうすることで錆の進行を食い止めることができるのです。
古い塗膜や錆を取り除くケレン作業はとても大変な作業になりますが、出来上がりの美観の観点からは絶対に外せない工程といえます。
その他の下塗り塗料
■フィラー
下地の凹凸を調整し、表面を平らに整える下塗り塗料です。
クラック(ひび割れ)がおきやすいモルタル外壁の下塗りに使われることが多く、フィラーでクラックを埋めて表面を整えます。
近年では微弾性フィラーと呼ばれるものが外壁塗装の下地処理に使わていて、塗膜に弾性を持たせる特徴をもつため、ひび割れ部分に入りこみひび割れをおこしにくくします。
■シーラー
塗装面にシーラーを塗り下地に吸収させることで、中塗りや上塗り用の塗料が下地に吸い込まれるのを防ぎ、表面と上塗り塗料との密着性を高めます。
外壁の痛みが強い場合は、シーラーの吸収が激しいので、二度塗りすることもあります。
まとめ
下塗り塗料は、塗装後の仕上りを左右するといわれるほど重要な工程の一つとなります。費用をかけて塗装工事を依頼するわけですから、仕上りに満足できないのでは意味がありません。施工する塗料の知識はもちろん、もともと塗られている塗料の知識、下地の痛み具合の判断から下地塗料の選別と、とても素人には対処できませんね。塗装工事は実績のあるプロに任せましょう。
2020年5月28日
スレート屋根とその他の屋根との違い
屋根のリフォーム工事では、スレート屋根を採用される方が多いです。なぜなのでしょうか?
ガルバニウム鋼板や瓦屋根と比較すると、どんなところにメリットがあるのでしょうか。
今回は、スレート屋根について詳しく見ていきましょう。
スレート屋根とはどんな屋根
スレート屋根と言われても、一体どんな屋根のことを指すのかわからない方も多いでしょう。
スレート屋根とは粘土板岩であるスレートを使用して作られた屋根のことです。
よく聞くカラーベストやコロニアルと呼ばれる屋根はスレート屋根の一種です。
スレート屋根の種類
石綿スレート
アスベストと呼ばれる石綿とセメントを混ぜて作られたものを石綿スレート屋根といいます。
2004年にアスベストが人体に有害と認定されるまでは一般的に使用されていました。
2004年以前に建てられた住宅が石綿スレート屋根である場合は、リフォーム工事をする際に廃棄物処理対策をしなければならず、費用がかさむことがあります。
無石綿スレート
石綿は使用せずに、パルプやビニロンを混ぜて作られたスレート屋根をいいます。
アスベストの使用禁止となった現在は、無石綿スレート屋根が多く採用されるようになりました。
天然スレート
スレート屋根の中で最も高いのが天然スレートです。
天然石を使用しているため高価になり、あまり日本では採用されていません。
人工スレート
人の手により人工的に作られたスレートをいいます。
使用する素材により特徴は変わります。
その他の屋根との違い
ガルバニウム鋼板と比較
ガルバリウム鋼板は、軽量で加工がしやすく、施工が簡単というメリットがあります。
耐熱性や遮音性はスレート屋根より劣ります。
コロニアルやカラーベストの方がガルバニウム鋼板よりも耐久性に優れています。
瓦屋根と比較
瓦は耐久性や耐熱性は高く優れていますが、価格が高くなります。
スレート屋根は耐久性、耐火性は瓦屋根に劣りますが、価格は瓦屋根の半分程度に抑えられます。
洋風の住宅には瓦よりもカラーバリエーションの豊富さから、スレート屋根を選ぶ方が多いです。
まとめ
スレート屋根にも種類があり高級感や重厚感を求めるなら断然、天然スレートがおすすめです。反対に価格重視で求めるなら無石綿スレートがおすすめです。デザインや商品数も多いので、自分好みの屋根を選ぶことができるでしょう。まずは、どの点を一番に重要視するかを、しっかり専門業者に伝えて最適な屋根材の提案をしてもらいましょう。
カテゴリ:屋根
2020年5月27日
外壁塗装中はエアコンは使えるの?
外壁塗装を検討されているお客様から、「塗装工事中はエアコンは使えるますか?」と、よく質問をされます。
真夏の暑い時期や、真冬の寒い時期にエアコンが使用できないとなると、日常生活に支障をきたします。
今回は外壁塗装時のエアコンとその他の機器使用についてご紹介します。

外壁塗装工事中にエアコンを使いたい!
外壁塗装中にエアコンを使用することはできます。
通常、外壁に近い室外機は塗料がかからないように養生シートやカバーで覆い塗装工事をします。この場合は空気が通らない養生になることが考えられます。
塗装工事前の打合せ段階で、「工事中にエアコンを使用したい!」と希望を施工業者に伝えることが大切です。
エアコンを使用したい場合は、エアコンが使用できるようにメッシュカバーなどで空気が通るように養生をしてもらう必要があるのです。
こうすることで、エアコンは基本的には使用可能になりましたが、外壁を高圧洗浄機で洗浄している時間は使用できません。室外機を通してエアコンに水が侵入してしまう恐れがあるからです。
事前の打合せで工程表を出してもらい、洗浄工程の日時を把握するようにしましょう。
塗装中の化粧カバーと室外機は?
エアコンの化粧カバーとは配管ホースを外壁のサイディングボードなどの色と合わした色で覆うカバーのことです。配管をサンドイッチするように挟み込んでいる部材で、簡単に取り外しができます。
■化粧カバー
化粧カバーは取り外し、カバーで隠れてしまう外壁部分も塗装をします。
■室外機
室外機と外壁の間にローラーや刷毛が入る隙間がある場合は、室外機の裏側も塗装します。

外壁と同じ塗料でカバーや配管ホースを塗装すると、外観がすっきり綺麗に仕上がるでしょう。
その他の機器は使える?
換気扇
換気扇を使用できるようにした場合、塗料の臭いが室内に入ってくる心配があります。
水性塗料を選ぶと油性塗料のようなシンナー臭はありません。塗料を選ぶ際に検討してみてはいかがでしょうか?
換気をしたい場合は施工業者に相談しましょう。
給湯器
給湯器の場合は養生している状態での使用はできません。
給排気設備を養生した状態で使用すると、着火不良を起こす危険があります。
そうはいっても、お風呂にも入るし食事もつくりますよね。事前に施工業者に何時~何時までは
使用しても良いかの詳細な打合せをしましょう。
まとめ
外壁塗装工事中もエアコンの使用ができることをわかりましたが、事前にエアコンを使用したい!という希望は伝えておかなければいけません。実際に工事が始まりエアコンが使用できないというアクシデントに巻き込まれないために必要です。
しっかりと要望を伝えて、丁寧な仕事してくれる業者へ依頼しましょう。
カテゴリ:外壁
2020年5月26日
梅雨前のメンテナンスが家を守る!
戸建て住宅、特に木造住宅は水から家を守ることが大切
一般住宅のうち、特に木造住宅は名の通り木材で建てられた家のことです。木材に水が侵入すると腐朽を起こしてしまいます。屋根の防水切れや外壁のコーキング切れにより雨漏りが生じると、木部がダメージを受けることとなり大切な家を守ることができません。
本格的な梅雨に入る前に、大切な家を守るために必要なメンテナンスを紹介します。
屋根材と漆喰
本格的な梅雨に入る前に、何らかの不具合を見つけた場合には梅雨の前に修理しておくのがオススメです。
■棟板金(専門業者に補修依頼)
スレートや金属屋根の場合は屋根の頂上部に棟板金が施工されています。釘やコーキングで固定されているため、経年劣化により固定していた部分が緩んでしまいます。固定部分が緩んでしまうと、その部分に隙間ができ水が侵入してしまいます。専門業者に補修依頼しましょう。
■屋根材の割れ(専門業者に修理依頼)
長く使用してきた屋根材は、割れやズレが生じている可能性があります。屋根材の割れやズレの部分から雨は容易に侵入してしまいます。梅雨前に修理を依頼しましょう。
■漆喰の劣化(専門業者に補修依頼)
瓦屋根の場合は、漆喰の劣化です。漆喰は施工から10年程度経過すると、ひび割れや脱落が目立つようになります。ひび割れや脱落の劣化部分から水の侵入を許してしまいますので、梅雨前に補修が必要です。
外壁のコーキングとメンテナンス
これからくる梅雨の時期、傷んだところからの水の侵入対策や外壁のカビ対策はとても重要となります。
■壁の目地部分コーキング(確認して業者に依頼)
多くの外壁材はサイディングボードが採用されていますが、ボードとボードの間には隙間剤のコーキングが施されています。残念ながらコーキングには寿命があり、経年劣化で機能を失ったコーキングは亀裂が起こったり最悪の状態では完全に剥がれてしまうこともあります。そのままの状態で放置してしまうと、その隙間から梅雨に入った雨が幾度も内部に侵入してくる事となり、木部は水を吸い湿気により腐って朽ちてしまいます。
コーキングに傷みを目視できた場合は、梅雨に入る前に早急に専門業者に修繕依頼をしましょう。
■定期的に水洗い(ご自身で)
普段のお手入れは水洗いで十分です。ホースで水をかけて柔らかいブラシやスポンジを使ってホコリや泥を洗い流しましょう。高圧洗浄機があれば、とても便利です。
洗った後は自然乾燥させますので、水洗いは天気の良い日に行いましょう。
定期的な水洗いだけでも、カビの発生はかなり抑えることができます。
■風通し良く(ご自身で)
特に北側の壁は日光が他面に比べると当たらず、湿度が高くカビが生えやすい環境です。壁面に近いところへは物を置かないようにしたり、植え込みがある場合は、こまめに刈り込みをし風通し良い環境にしましょう。
湿気によって劣化する床下
■シロアリ(専門業者へ依頼)
湿気の多い場所を好み住宅に被害を与えるのがシロアリです。
シロアリは湿気を含んだ木材を餌としていることから、梅雨時期には被害を受けることも考えらえます。
特に築年数が経った住宅には注意が必要です。シロアリ対策は専門業者へ依頼しましょう。
■床下に湿気が溜まる(専門業者へ相談)
床下が木材でできている住宅の場合には、梅雨時期の湿気対策が必要です。
カビは湿気の多い場所を好むため、床下に湿気が溜まった状態が続くとカビが生えてきてしまいます。目視で床下を確認するのは難しいですが、押入や床、畳からカビの臭いがすると要注意です。床下の木材がかなり水分を吸い込んでいる可能性が高いです。
床下の木材が水分を含むと、木材の腐食が始まり強度は損なわれ家全体の耐久性に影響します。
湿気防止シートの設置や床下換気扇の設置は、専門業者へ相談しましょう。
まとめ
本格的な梅雨に入る前に、お家のメンテナンスをしましょう。
雨漏りや、シロアリ被害は起こってしまってからではコストも高くなり、健康に被害が及ぶこともあります。
定期的なメンテナンスを心がけて大切な家を守りましょう。